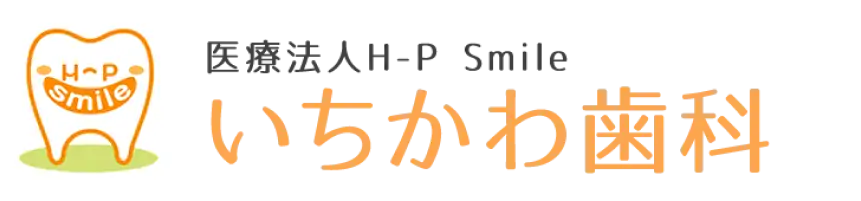口腔外科とは

口腔外科は、虫歯や歯周病以外の、口や顎の病気に対して外科的な治療を行う専門分野です。代表的な治療として、親知らずの抜歯が挙げられます。
親知らずは生え方が複雑だったり、神経や血管と近接している場合もあり、専門的な技術が必要です。
口腔外科では、親知らずの抜歯以外にも、外傷による歯の損傷、顎の骨折、歯茎の凸凹の改善など、歯茎より更に深い位置にある個所の治療など幅広く口腔内の外科治療に対応します。
こんな方におすすめ

- 親知らずが腫れて痛みを感じるので抜歯したい
- 顎が痛くて口を開けるときに痛みがある(顎関節症)を治したい
- スポーツ中に接触があり歯が抜けた、唇が切れた
- 噛み合わせのための抜歯をしたい
- 歯ぎしり・食いしばりで困っている
このようなお悩みがございましたら、いちかわ歯科にご相談ください。
口腔外科で扱う主な症状

口腔外科で扱う主な症状は次の通りです。
- 親知らず
- 顎関節症
- 不正咬合
- 噛み合わせの異常
- 歯茎や顔の腫れ
- 外傷
- 口内炎
- 口唇口蓋裂
- 神経性の疾患
- 嚢胞・腫瘍
- 唾液腺の疾患
- 口腔がん
親知らずの抜歯は一般歯科でも扱っていますが、歯根の先が折れ曲がっていたり、親知らずが横向きに埋まっていたりするような場合では通常の処置では対応できない場合があります。当院でも抜歯に際してリスクの高い親知らずは、近隣の専門の口腔外科もしくは口腔外科のある病院を紹介しています。
顎関節症でお悩みの方には、マウスピースの作成や、顎の関節の調整を行います。痛みや開口の制限などの症状を改善することで、頭痛や肩こりなどの全身症状の回復も期待できます。
親知らずについて

親知らずは成人前後に生えてくる最後の歯で、生え方には個人差があります。中には顎の中に埋まって中途半端に生えてしまったり、斜めや横向きに生えてしまったり、そもそも親知らずが生えてこない人もいます。
親知らずは必ずしも抜歯の必要があるわけではありませんが、炎症を起こして腫れたり、親知らずの隣の歯が虫歯になったりする場合は、抜歯をおすすめしています。
親知らず以外の抜歯が必要になる場合は?
- 虫歯や歯周病が進行しており保存が困難
- 隣の歯や周りの歯に影響がある
- 炎症を起こして腫れている
- 粘膜を傷つけている
多くの場合は、虫歯や歯周病が進行したために歯そのものの保存ができない場合や、細菌感染などでほかの歯や歯茎に影響を与えている場合などです。また、食事のときに痛くて噛めなかったり、粘膜を刺激して傷になってしまったりするときも抜歯を検討します。
歯冠延長術
歯茎より深い位置にある治療箇所を改善する口腔外科治療を歯冠長延長術(クラウンレングスニング)と言います。
歯ぐきの切開や歯槽骨(歯を支える顎の骨)を削る治療によって歯茎の位置を下げ、歯根を露出させることで、歯茎より上に歯がある状態をつくり、歯を抜かずに長期安定した被せ物が可能な状態にします。
他にも歯冠延長術を行うことにより下記の効果が見込めます。
- 被せものが外れにくくなり、虫歯の再発予防につながる
- 歯周病が発生しにくい環境になる
歯肉形成(歯肉整形)
- 歯茎が下がっている箇所がある
- 歯が長くなってしまって歯がしみる
- ガミースマイルがコンプレックスなので改善したい
歯の再植
当院では根管治療では治らなかった場合や、歯が垂直に割れてしまっているケースには歯の再植(意図的再植術)を提案しております。
問題となる歯を一度抜歯し、口腔外で処置した後に元の場所に戻すことによって、インプラントや部分義歯を回避し、ご自身の歯で延命を図る治療です。
大切な歯を保存するために行う、一つの治療法です。
意図的再植術の一番の特徴は、ご自身の歯を保存できることにあります。治療には条件がありますが、適合すればご自身の歯を活かす有効な手段になります。
当院では「歯を残す」ことを一番の前提に置いてカウンセリングや治療を行っておりますので他院で「抜くしかない」と言われた方もご相談ください。
口腔外科の治療までの流れ
下記は親知らずの抜歯における治療の流れです。
歯冠延長術、歯肉形成、歯の再植に関する治療の流れは当院のスタッフ・医師にお問い合わせください。
診察
診察ではまず口腔内を診査し、親知らずの生え方、周囲の歯の状況を確認します。
検査
レントゲンや、必要に応じてCT撮影を行い、親知らずの位置、深さ、神経との距離などを詳細に確認します。これらの検査結果から、抜歯処置の難易度や合併症のリスクの有無などを説明します。
表面麻酔
表面麻酔薬を歯肉に塗布します。これは、注射による麻酔の痛みを軽減するための処置です。表面麻酔薬は粘膜を麻痺させ、注射針の刺入時の痛みを緩和します。この後、局所麻酔薬を注射し、抜歯部位を完全に麻痺させてから、抜歯を行います。
抜歯
親知らずの抜歯は、歯の状態によって方法が異なります。通常はペンチのような抜歯鉗子と呼ばれる器具を用いて抜きますが、歯ぐきに埋まっている場合や、横向きに生えている場合は、歯ぐきを切開したり、歯を分割したり外科的な処置が必要になることがあります。
いずれの場合も、事前に麻酔を行いますので、痛みを感じる心配はほとんどありません。
止血
抜歯後、出血を止めるためにガーゼを強く噛んで圧迫します。通常は5分ほどで止血しますが、出血が多い場合は、縫合をして傷口を閉じる場合があります。